こんにちは!
もってぃです!
今週末に1500mの記録会に出場するので、今回は理想的なペース配分について考えていきたいと思います!
理想的な1500mのペース配分
スタート時(60m)

一般的に1500mのレースではスタートして60mは位置取りを決めるためにハイペースでスタートすることが多く、60m以内が理想とされています。
では、なぜ60mなのでしょうか?詳しく見ていきましょう!
筋肉を動かすためのエネルギー源として最初に使われる回路はクレアチンリン酸系と言われるもので、筋肉に貯蔵されているクレアチンリン酸をクレアチンとリン酸に分解することで発生するATP(エネルギー)を利用して筋肉を動かします。
この回路は10秒ほどしか持続せず、その後は解糖系→TCA回路(有酸素回路)の順に回路が回っていきます。
この3つの回路の中でもっとも容易に素早くエネルギーを発生するのがクレアチンリン酸系にあたります。
中長距離走において、走り始めにトップスピードに達するというのはこのためです!
ちなみに、100m走のトップ選手のタイムは9秒~10秒にあたりクレアチンリン酸系が大半を占めます。
話を戻して、1500mにおいて理想的な位置取りする時間は10秒以内(60m)にあたり、クレアチンリン酸系が占める割合が大きいと考えられます!
では、なぜクレアチンリン酸系の割合が大きい10秒以内(60m)が理想とされているのでしょうか?
中長距離選手にとって位置取りのためにスタートダッシュする場合、ほとんどの選手がスタートから10秒が60mにあたり、それ以降の距離は10秒を超えクレアチンリン酸が枯渇します。
次に、使われる回路が解糖系にあたるわけですが、この回路の過程で一般的に言われる乳酸がたまると言った現象が起きます。※乳酸は筋疲労に直接的につながらない。実際の原因はPHの減少。
(乳酸=足を動かなくしているというのは誤りであるというのは前回のブログで話していますが、今回はわかりやすくするためにこのような表現にしています。実際はPHの減少です。)
したがって、スタートから60m以降の位置取りは、解糖系を使用してしまい、後半のバテにつながってしまうことが考えられています。
1週目(60m~400m)
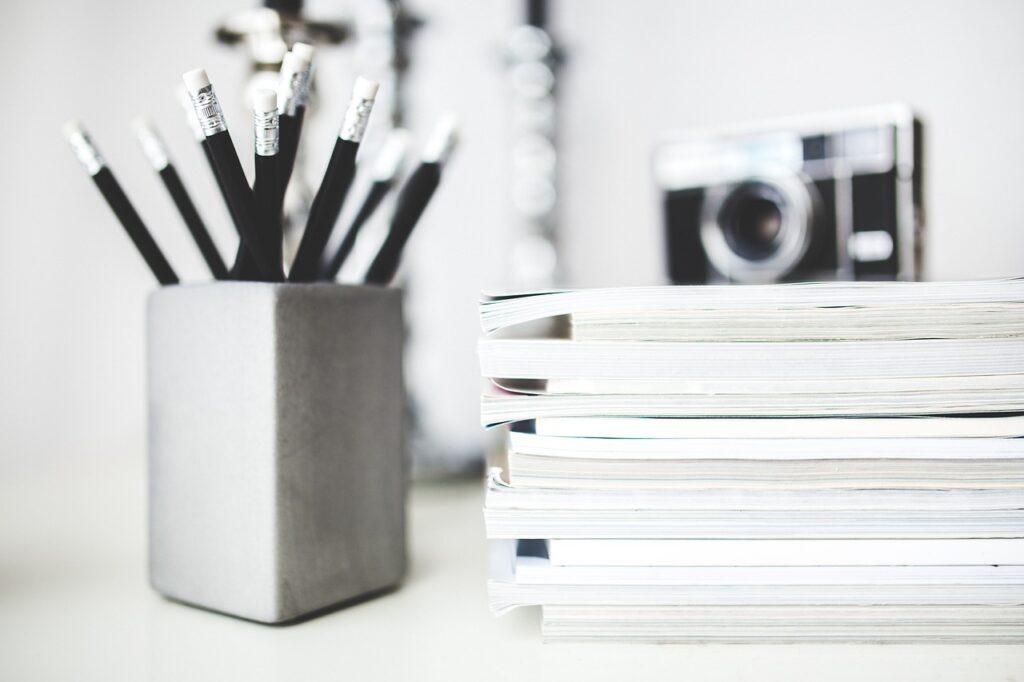
60m以降はレースペース±1秒以内が望ましいと考えられています。
欲を言えば、60mまでの位置取りで、自分が定めたペース帯の集団に着いていくことが理想的です。
先頭に立って、レースを進めるのは風の影響を受けやすく、エネルギーを多く使います。
前にいる選手の背後に回り込み、風の影響を受けない場合、vo2が6.5%低下するといわれています。(ランニングやウォーキングにおける風の抵抗の影響と、水平または垂直の力に対する作業の機械的効率 – PMC)
また、先頭を走ることは心理的負荷が大きいと考えられます。
先頭を走れば、ペースメイクするのも自分であり、前に標的物もないので、頭で考えることが多くなります。
それに対して、自分のレースペースと同じ選手の後ろにいた場合、「この選手に着いていく」ということだけ考えるだけでよく、目線が前の選手の背中に注目するのでゾーンに入りやすくなります。
陸上においてもゾーンは存在し、考えること減らせば減らすほどゾーンに入りやすくなるといわれています。
2週目(400m~800m)

2週目でラップタイムが大幅に落ちた場合、ラストスパートで挽回するのが難しいと考えられており、イーブンペースで走ることが求められます。
また、2週目は欲を言えば1週目同様、前の選手の後ろを追尾する走りが望ましいと考えられます。
2週目は1500mにおいて苦しい距離帯であり、前の選手に引っ張ってもらう方が好タイムが期待できます!
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
それは、集団のペースががっくり落ちることです。
この文献で紹介されている一流の中距離女子選手でも2ラップ目のタイムが落ちています。(2006_20.pdf)
これは、男子選手でも同じことが言えるでしょう!
私も1500mのレースに何度か出場していますが、1週目と同じような感じで走るとラップタイムが4秒程度も落ちていることがざらにあります。
したがって、イーブンペースで走るために、2週目はラップタイムを2秒ほど上げるイメージで走ることが理想とされていることが多いです。
2秒上げるイメージで走ってやっとイーブンで走れるぐらいにになるため、一流の選手もこのようなイメージで走っているに違いないと私は考えています。
これは、実際に1500mのレースで先頭を走って経験したことと、ほとんどの先頭選手がラップタイムを4秒ほど落としている場面を多く見ていることからこのようなことが考えられます。
このような傾向がある2週目ですが、イーブンペースで走る(スピード維持)が記録向上のための絶対条件であります。
しかし、先頭の選手が2秒上げるようなイメージで走っていない限り、ラップタイムの低下が考えられ、スピードが落ちていれば、自分の判断で先頭を引っ張る必要性が出てきます。
先頭に出るかでないかの判断は、集団を引っ張る選手の能力レベルによるので、難しい判断になります。。
スタートリストの選手に強い人が入れば、2週目はその選手が理想的なラップを刻んでくれる可能性が高いため、その選手に追尾し続ければ、風の影響を受けず、エネルギーを無駄に消費しないまま3ラップ目につなげることができるかもしれません。
強い選手がいない場合は、2週目はペースが落ちれば、先頭に出て走る意識を持っておいた方が良いかもしれません。。
※周りの選手が自分より断然いい場合、2週目も3週目も何も考えずに追尾することだけを考えれば、ベストが出ます!
3周目(800m~1200m)

3周目からは息が上がり始め心拍数が急増することが予想されます。
また、有酸素能力が弱い選手は脱落し始めるのが3周目(800m~1200m)です。
TCA回路(有酸素回路)は一般的に2分を超えた辺りから回り始めるといわれています。
有酸素回路は名前の通り、エネルギーを生成するために酸素を有するため、息が上がり、心拍数が上がります。
800m通過は全日本陸上標準記録ペース(3分45秒)であればちょうど2分に値するため、ほとんどの選手のエネルギー回路は有酸素回路(クエン酸回路)を占める割合が大きくなります。
3周目時点は解糖系の回路を使っており、有酸素回路の割合が増え始めるため、足が動かない+呼吸がきつくなるといった症状が出てきます。
したがって、この周は足が動かないし、呼吸も辛いけど、とにかく耐える気持ちが大切です。
もしも2週目のラップが悪ければ、取り返すつもりで走り、2週目に目標ペースで走ることができた人は同じペースを維持できるよう耐える気持ちで走ると良いと思います!
また、1100m地点では残り1周を迎えるため、一気にギアを切り替えてペースを上げることを意識します。
残り300m(1200m~1500m)

この場面は、ラスト1周の鐘が鳴って100m進んでいるような状態(バックストレート手前)です。
記録を出すことを目標としているのであれば、残り400m地点(残り1周)からペースをあげ、残り200mから2段階スパートで出し切る気持ちで走ると良いと私は考えています。
どの段階で、スパートをかければ、ベストが出るかは自分の型(スピード型かスタミナ型か)とこなしてきた練習の質によって変わると思います。
対照的に、優勝や入賞を狙うような大会では、自分の得意なスパート方法を選択すると良いでしょう!
(スピードに自信がある選手はラスト100mで仕掛けたり、持久力に自信がある選手はラスト400mで仕掛けたりなど)
世界陸上や全日本陸上を見ていて、スピード型の選手が最後に刺す展開が多いように思いますが、残り300mや400mのロングスパートで逃げ切る選手の試合も頻繁に目にします。
順位を狙うような試合ではレース展開の正解はないと私は考えております。
まとめ

どうだったでしょうか?
私も、明日1500mのレースがあるのでこのようなレース展開をイメージしながら走ることができたらなと思っています!
どのスポーツもそうですが、「意識しろ」と言われていたとしても、いざ本番になると何も実践できないことがほとんどですよね(笑)
このようなことは体に染み込ませないと難しいので、とにかく全力で練習頑張って、全力でレースに臨んでいれば、良い結果が出てくるのではないかなと思います!
私も、いざ本番になると、何も意識できなくなると思いますが、とにかく全力で頑張りたいと思います。
意識するのは大切ですが、あまり頭を使うとゾーンに入りにくくなりますから、何も考えずにレースに身を任せてた方が良いのかもしれません!?
このブログが少しでも皆さんの役に立てば幸いです!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42edfc4f.ea3f5d0f.42edfc50.58ec3afc/?me_id=1235915&item_id=10083008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-free-stylers%2Fcabinet%2Fjersey12%2Fset24206bb.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


